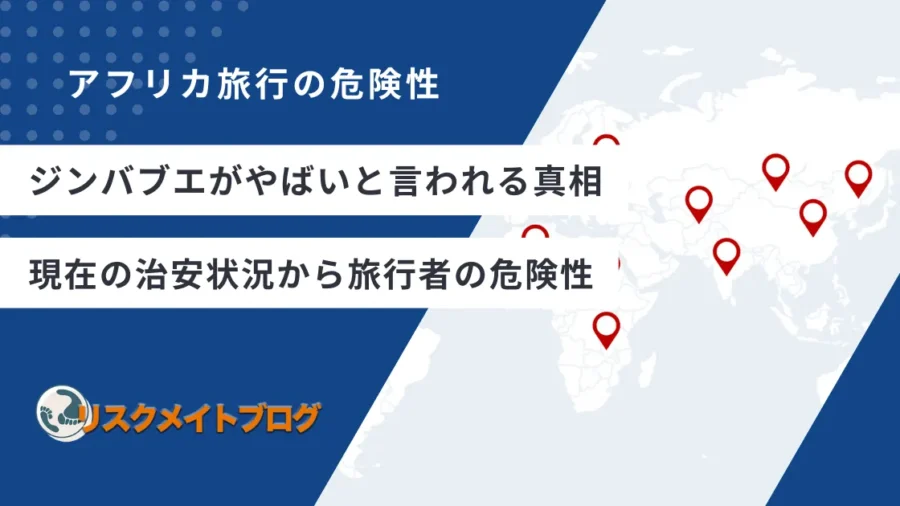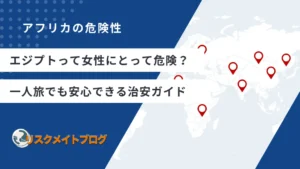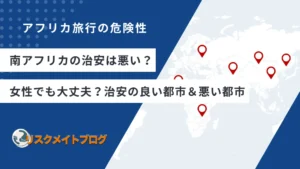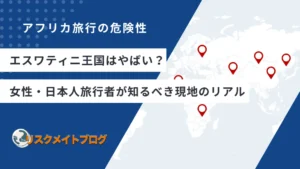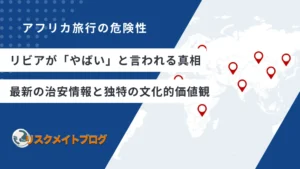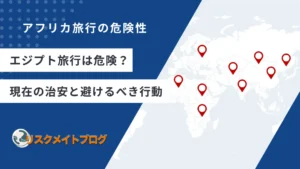「ジンバブエ」と聞いて、あなたは何を思い浮かべるでしょうか?
アフリカ南部に位置し、壮大なビクトリアの滝や野生動物にあふれた自然豊かな国。そんなイメージを持つ人も少なくないはずです。
しかし同時に、「治安が悪い」「通貨が信じられない」「旅行者に危険」など、ネガティブな情報が飛び交う国でもあります。
実際に「ジンバブエ やばい」と検索する人が増えている今、果たしてその「やばさ」とは具体的に何を意味するのか?
本記事では、ジンバブエの現在の治安、経済状況、文化的リスク、観光トラブルまでを総ざらいし、旅行者が本当に知っておくべきリアルな情報を徹底解説していきます。
ジンバブエが「やばい」と言われる理由とは?
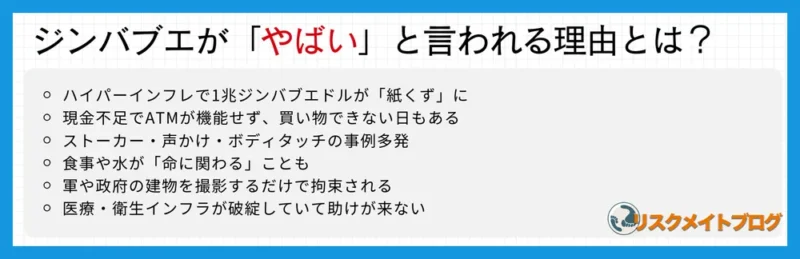
ジンバブエが世界中の旅行者から「やばい国」として語られるようになった背景には、単なる治安の問題だけではなく、経済破綻・インフラ崩壊・文化ギャップ・人権問題といった複合的な課題があります。
この章では、ジンバブエを「特殊なリスク国」にしているいくつかの要素を、ひとつずつ具体的に見ていきます。
ハイパーインフレで1兆ジンバブエドルが「紙くず」に

ジンバブエといえば、何と言ってもまず語られるのが世界最悪とも言われたハイパーインフレです。
2000年代後半、政府の経済政策失敗や通貨乱発が重なり、インフレ率は年率2億パーセントを超える異常事態に突入。
その結果、1兆ジンバブエドルという桁外れの紙幣が発行されるも、市場価値はほぼ「紙くず」同然になりました。
レストランで昼食を食べ終えた頃には、支払金額が数十倍になっている。
タクシーを降りる時に「値段が変わった」と言われる――。そんな冗談のような現象が、現実に起きていたのです。
このインフレ問題はその後、米ドルや南アフリカランドなどの外貨導入でいったん沈静化したものの、再び「自国通貨復活」が裏目に出ており、不安定な経済状況は継続中です。
現金不足でATMが機能せず、買い物できない日もある
ジンバブエでは今なお、現金が手に入らないという深刻な問題が続いています。
通貨が信頼されていないため、銀行に預け入れる人が少なく、結果としてATMに現金が補充されず、「ATMに並んでも現金が引き出せない」「クレジットカードも使えない」という状況が日常茶飯事です。
旅行者にとって最も困るのが、飲食店やホテル、商店で「キャッシュ・オンリー」が当たり前なのに、そのキャッシュが調達できないという事態。
さらに、黒市場での両替を余儀なくされる場合もありますが、そこでの詐欺被害やトラブルも多発しているため、非常にリスクが高いのです。
つまり、ジンバブエでは「お金を持っていても使えない」「現金が手に入らない」という矛盾した危険が、旅行者を待ち受けています。
ストーカー・声かけ・ボディタッチの事例多発
ジンバブエでは、観光客、特にアジア系や白人女性に対する過剰な声かけや接触行為が頻繁に報告されています。
一見フレンドリーに見える現地の人々の振る舞いも、度を越すとストーカーまがいの行為に変わることがあり、女性旅行者にとっては非常にストレスフルで危険な環境になることも。
- 「写真を撮らせて」と近づいたあと、しつこく連絡先を聞かれる
- 「案内してあげる」と言いながら、勝手に付きまとってくる
- 市場や混雑エリアでのボディタッチ(手を握られる、腰に手を回される)
これらの行為は、リスクを感じた時点で即座に距離を取り、毅然とした態度ではっきり「NO」と伝えることが重要です。
また、女性が単独で夜間外出をすることは絶対に避けるべきであり、行動はできる限り日中・複数人で行うようにしましょう。
現地では性的な同意やパーソナルスペースの認識が日本とは大きく異なるため、「日本の常識」が通じないことを前提に立ち回る必要があります。
食事や水が「命に関わる」ことも
ジンバブエ旅行で気をつけなければならないのは、治安だけではありません。
飲食による健康リスクが極めて高いというのも、見落としてはならない「やばさ」のひとつです。
特に地方やローカルな飲食店では、以下のような衛生問題が深刻です。
- 水道水はほぼ飲用不可。煮沸してもリスクが残ることもある
- 生野菜や生肉は細菌や寄生虫感染の原因になる
- アイスやジュースに使われる氷も、未処理の水で作られていることが多い
旅行者が実際に体調を崩しやすいのは、腸チフス・コレラ・赤痢・アメーバ症などの消化器系感染症で、嘔吐や高熱に苦しみながらも、医療を受けられずに回復を待つしかないという状況も珍しくありません。

安全な旅行を確保するためには、
- ペットボトル入りの水以外は絶対に口にしない
- 観光客向けの信頼できるレストランを選ぶ
- 野外の屋台や路上販売の食べ物には手を出さない
など、基本的なリスク管理を徹底することが不可欠です。
軍や政府の建物を撮影するだけで拘束される

ジンバブエは政情が不安定であり、政府機関や軍に対する警戒感が非常に高くなっています。
そのため、公共施設の撮影行為が「スパイ行為」として扱われることがあるのです。
具体的に危険とされる撮影対象には以下が含まれます。
- 軍事基地や兵士の姿
- 大統領官邸、政府機関の建物
- 国旗や国章が掲げられた公共施設
観光客がスマホで建物を撮っただけでも、その場で取り押さえられ、パスポートを確認された上で拘束された事例が複数報告されています。
最悪の場合、機器の没収や国外退去処分になることもあるため、ジンバブエ国内ではカメラやスマホを向ける前に必ず周囲を確認し、危険があれば撮影をやめる判断力が必要です。
医療・衛生インフラが破綻していて助けが来ない
ジンバブエでは、病院や診療所といった医療機関そのものが慢性的な機能不全に陥っている状態が長く続いています。
その原因は、長年にわたる経済破綻、政府の腐敗、不安定な電力供給、そして医療人材の国外流出です。
旅行者が体調を崩したとき、以下のような問題に直面する可能性があります。
- 病院が開いていない、または医師が常駐していない
- 医薬品が不足しており、抗生物質すら入手できない
- 医療費は事前支払いが必須なのに、カードも現金も使えない
- 設備が老朽化していて清潔とは程遠い環境
また、交通インフラの問題も重なり、救急車を呼んでも来ない、あるいは有料で高額請求されるといったケースも発生しています。
万が一の際には、自力での移動・対応が求められるという点でも、旅行者にとっては非常に過酷な環境です。
さらに衛生面でも問題が山積しています。首都ハラレですら下水処理が不十分で、雨季には飲料水が汚染されて水系感染症が蔓延するリスクが高まります。
事実、2023年にはコレラが再び流行し、複数の死亡例が報告されました。
結論として、ジンバブエでは「何かあったら病院に行けばいい」という考え方は通用しません。
旅行前には海外旅行保険に必ず加入し、持病がある方や体力に不安がある方は、訪問自体を再考する価値があります。
ジンバブエの「現在」をわかりやすく解説
「ジンバブエは昔ほど危なくない」と思っている人もいるかもしれません。
たしかに一時期のような完全な無政府状態からは脱したものの、現在もなお、国としての「土台」がぐらついたままの危険なバランスの中で生活が成り立っています。
この章では、そんなジンバブエの2025年現在の「現実」を、旅行者が直面する可能性の高い視点から具体的に解説していきます。
3つの通貨が並行流通している混沌とした経済状況

ジンバブエはかつて、インフレを止めるために米ドル、南アフリカランド、ユーロなどの外貨を法定通貨として受け入れた異例の国です。
その後、自国通貨であるジンバブエドル(ZWL)を復活させたものの、信用を回復できず、結果として現在は:
- ジンバブエドル(ZWL)
- アメリカドル(USD)
- 南アフリカランド(ZAR)
この3つの通貨が同時に出回っている「通貨カオス状態」となっています。
しかも、支払う側と受け取る側の「どの通貨が使えるか」「レートはいくらか」が毎日変動するため、観光客にとっては非常にストレスフルな環境です。
たとえばこんな状況が起きます。
- レストランではUSDしか受け付けないが、ホテルではZWL払いを求められる
- 市場では「ZWLなら倍の値段」と言われる
- 両替商の言い値で1日ごとにレートが変動する
つまり、ジンバブエでは「お金がある」=「安心」ではなく、「どの通貨でどう払えるか」が最大の問題になるのです。
電力・水道は不安定、停電・断水は毎日が当たり前
都市インフラの維持も、ジンバブエでは極めて困難な課題です。
特に深刻なのが電力と水の供給で、「計画停電」ではなく「日常的な停電と断水」が繰り返されています。
例えばハラレ市内では、
- 朝5時から午後3時までの停電が週5日続く
- 蛇口をひねっても水が出ないことが週に数回ある
- ホテルのシャワーが「冷水のみ」になる
といった状況が「普通」に起こります。
旅行者が安心して過ごすには、「停電しても自家発電があるホテル」や「ボトル水を常備してくれる施設」を事前に調べて予約することが重要です。また、電子機器の充電タイミングや、ネット環境の不安定さにも配慮しておく必要があります。
一見穏やかだが「裏通り」に危険が潜む都市事情
ジンバブエの街並みは、表面上は比較的落ち着いて見えることがあります。
実際、首都ハラレや観光地のビクトリアフォールズは緑も多く、日中は平和そのもののように感じられるかもしれません。
しかし、その「安心感」が油断を生み、トラブルを招くことが少なくありません。
特に以下のような場所では警戒が必要です。
- バスターミナルの裏手や人気の少ない路地
- 市場(バザール)周辺の狭い通り
- 「ガイド」を名乗る人が多く集まる観光ポイント
日中でも「スリ」「声かけ詐欺」「荷物を持って逃げるトラブル」が起きており、また夜間になると照明も少なく、治安は急激に悪化します。
大切なのは、「見た目の静けさ」を信用しすぎないこと。
昼でも人の少ない道は避け、必ず複数人または現地ガイドと一緒に行動することが安全への第一歩です。
ジンバブエ旅行で観光客がよく遭うトラブル

ジンバブエを訪れる外国人旅行者の多くが、「事前に聞いていた以上にトラブルが多い」と口をそろえます。
それは単なる運の問題ではなく、現地特有の事情や文化、制度の不備によって「予測可能なトラブル」が多発しているということです。
ここでは、ジンバブエを旅行中に観光客が実際によく遭遇する具体的なトラブルとその背景を、分かりやすく解説していきます。
警官にチップを請求される「検問詐欺」
ジンバブエでは、交通検問の多さが観光客にとっての悩みのタネです。
国道や街中の主要道路では頻繁に検問が実施されており、車を止められた際に身分証やパスポートの提示、荷物検査を求められることがあります。
この際、何も違反がないにも関わらず、「手続きに時間がかかるからチップをくれ」「通行税が必要」などと言われて金銭を請求されるケースが多発しています。
中には正規の警官ではなく、制服を着た「ニセ警察」による詐欺まがいの検問も報告されています。このような場面では、
- 毅然と対応し、現金を渡さないこと
- 明細書や領収書の提示を求めること
- 可能であれば車内から出ないこと
が鉄則です。とはいえ相手が実際に権力を持っている場合もあるため、無理な抵抗は避けつつ、危険を最小限にするための「慎重な断り方」が求められます。
市場での「外国人価格」による不当請求
ローカル市場では、観光客を対象に「外国人料金」が自動的に適用されることが多くあります。
たとえば、水1本が地元の人には50セントでも、外国人には3ドルと吹っかけられる、という具合です。
交渉文化が根付いているジンバブエでは、定価が表示されていないことがほとんど。そのため、旅行者は常に価格交渉をする前提で買い物をする心構えが必要です。
- 事前にホテルスタッフなどに相場を聞いておく
- 英語で明確に「高すぎる」と伝える勇気を持つ
- 値段交渉ができない場合は潔く別の店に行く
また、「買った後に「足りない」と追い請求される」パターンもあるため、支払い時にはその場でしっかり金額確認をすることが大切です。
ドローン持ち込みでの拘束・没収トラブル
意外と見落とされがちなのが、ドローン(無人航空機)の取り扱いに関する規制です。
ジンバブエでは、ドローンを持ち込むこと自体は違法ではありませんが、許可なく飛ばすことは非常に厳しく禁止されており、特に空港・政府関連施設・観光名所周辺ではリスクが高いとされています。
実際に、ドローンを所持していた日本人旅行者が、
- 空港で中身チェックの際に没収された
- 飛行させて軍の施設を誤って撮影し、拘束された
- 許可書がないとして罰金や長時間の事情聴取を受けた
といったトラブルを経験した事例もあります。
ドローンを使いたい場合は、必ず事前にジンバブエ民間航空庁(CAAZ)へ申請し、正式な許可書を取得してから入国するようにしましょう。そうでない場合は、持ち込まないのが最も安全です。
現地SIMが機能せず、連絡手段が絶たれる
ジンバブエでは、携帯ネットワークの整備状況が極めて不安定で、空港で購入したSIMカードが現地で使えない・アクティベートできないといったトラブルも珍しくありません。
また、通信業者によっては政府の検閲が入っており、SNSや地図アプリへのアクセスが制限されることもあります。
電波の届く範囲が限定されていたり、停電時に基地局が落ちてしまうケースもあるため、緊急連絡手段としてはまったく頼りにならない場面もあるのです。そのため、対策としては、
- eSIMやポータブルWi-Fiなど「予備の通信手段」を準備しておく
- オフライン地図や翻訳アプリを事前にダウンロードしておく
- ホテルのフロントで「最寄りの通信ショップ」を確認しておく
などの工夫が求められます。
ジンバブエでは「スマホがあれば何とかなる」は通用しません。「つながらない前提」で旅のプランを組むことが大切です。
よくある質問
ジンバブエといえば、かつて世界中のメディアを騒がせた「100兆ドル札」など、インパクトの強い話題が多い国です。
この章では、旅行者や関心を持つ人々からよく寄せられるジンバブエに関する素朴な疑問とその答えを、わかりやすくお届けします。
ジンバブエドルが暴落した理由は何ですか?
ジンバブエドルが世界最悪レベルのハイパーインフレを経験した主な理由は、以下の3つに集約されます。
政府が財政赤字を埋めるために、裏付けのない紙幣を大量に発行しました。これにより通貨の価値が一気に下落し、物価が異常に高騰しました。
2000年代初頭、ムガベ政権が白人農家の土地を強制収用したことで農業が壊滅。食糧不足が進行し、物資不足とともに市場経済が混乱しました。
欧米諸国からの経済制裁により、外資流入が止まり、金融システム全体が崩壊。国際的な信頼を失い、外貨準備が枯渇しました。
これらの要因が複雑に絡み合い、年率数百万パーセントという異常なインフレ状態に突入。最終的には自国通貨を事実上放棄せざるを得ない状況に追い込まれました。
100兆ジンバブエドルは日本円でいくらですか?
結論から言うと、ほとんど無価値です。
一時期発行された「100兆ジンバブエドル紙幣」は、ハイパーインフレの象徴として世界的に有名になりましたが、現在では公式な通貨としての価値はありません。日本円換算でいうと、
- 額面:100兆ZWD
- 現在の価値:0円(紙くず)
ただし、面白いのはこの紙幣が「お土産」や「コレクターズアイテム」として世界中で売買されているという点です。
観光地のマーケットやオンラインショップでは1枚数百円〜数千円で取引されていることもあり、経済価値としては消えたものの、象徴的価値を持つ「通貨の亡霊」ともいえる存在となっています。
まとめ|ジンバブエを旅するなら「知識と覚悟」が必須
ジンバブエという国には、ビクトリアの滝や手つかずの自然といった壮大な魅力があります。
しかしその一方で、経済の崩壊、インフラの不安定さ、観光客を取り巻く文化的・制度的リスクが存在しており、軽い気持ちで訪れるには「ハードルが高すぎる国」とも言えるでしょう。
ここまで紹介してきたように、ジンバブエ旅行では、
- 通貨の信用がなく、現金すら手に入らない日がある
- 公共インフラが機能しておらず、電気・水・通信に常に不安がある
- 観光客をターゲットにした詐欺や不当請求が日常化している
- 医療・衛生環境が劣悪で、病気や怪我が命に関わることもある
という現実が待ち受けています。
しかし、「それでも行きたい」という人がいるのもまた事実。
その場合は、リスクを正しく理解し、あらかじめ知識を備え、適切な準備と覚悟をもって旅に臨むことが絶対条件です。同時に、現地の文化や価値観に敬意を払い、過度に期待しすぎないことも安全に旅をするための重要なポイントです。
ジンバブエ旅行は「冒険」に近い体験です。だからこそ、危険の裏にある感動を手にするためには、リスク管理が何よりのパスポートになるのです。